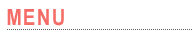皮膚と漢方
| 漢方/漢方医 | 金匱会診療所見聞録(1) | 金匱会診療所見聞録(2) |
| 金匱会診療所見聞録(3) | 金匱会診療所見聞録(4) | 金匱会診療所見聞録(5) |
| 金匱会診療所見聞録(6) | 金匱会診療所見聞録(7) | 金匱会診療所見聞録(8) |
| 金匱会診療所見聞録(9) | 金匱会診療所見聞録(10) |
漢方/漢方医
こまやかな診察でカラダの歪みを知る。 専門医ならではの治療はいかがですか。
西洋医学とは違い、からだのどこがどんな状態になっているか、と診察するのが東洋医学!
皮膚病だからと言ってお肌のことだけでなく全身からの治療のアプローチ。 実際に体験してみてはいかかですか!?
漢方診療を体験!
- 問診: 気になる症状、からだ細部の状態だけでなく、食生活、睡眠など生活習慣にわたるまでかなり細かく質問が用意されている、それをもとに先生の診断がスタート。
- 脈を診る: 脈の診方は独特だ。 3本の指を使って、両手首合わせて6か所の脈をとる。 どこの脈が強く打っているか、速さはどうかを診る。 脈が強い箇所は実、速ければ熱、というふうに診断。


- 腹部を診る
おなか全体を軽く手のひらで圧す。 「圧して痛いところには瘀血や炎症があります。 全体的に力強いのは実証、弱々しいのは虚証。 胃に水がたまっていればチャプチャプ音がします。」


- 症 例: 普通の治療では治り難いニキビ。生活やストレスに伴って出てくるシッシン・肌荒れなどカラダに合った漢方薬で良くなる例もたくさんあります。
- 効能について: 処方された漢方薬を、市販されている本などで調べると効能が記載されていなかったりしても、それ以外にも効果が得られるものもあるので、患者さんにもっとも適した処方をしていますが、もっと詳しくお知りになりたい方は遠慮なくお聞き下さい。
また同じ症状でも人によっては処方する漢方薬がかわる場合がありますので、他の人から貰ったりして服用しないようにご注意ください。
金匱会診療所見聞録(1)
『水沢医師会報』2000年4月号掲載より
-金匱会(キンキカイ)診療所とは?-
金匱会診療所!? - 多くの本医師会会員がご存知ない名前だと思う。 かく言う私もつい一年前までは知らないでいた。なんと日本最初の漢方医療施設なのである。 つまり漢方の話なのだ。
漢方については本会員の中に桜井先生、木村先生、大歳先生といった古くから漢方薬を日常診療に取り入れた先生方がおられるので、私が説明するなどは身のほど知らずのことなのではある。 しかし、かっての自分を考えると知らない先生もおられると思うので敢えて触れさせて頂くことにする。
現在の日本の漢方は大きく三つの流れがある。 一つは「和漢」で日本伝統の漢方である。 もう一つは「中医」と言われる現代中国の伝統医療で、特に1970年代日中国交正常化以降多くの情報が入るようになった。 そして最後に「その他」と言うべき、1976年の漢方エキス剤が薬価基準に収載され、保険に採用され、講習会や書物から独自に勉強されて、西洋薬的使用の延長線上でエキス剤を使用されている先生方である。 去年の日医ニュースの中に、漢方薬の処方経験を持つ医師は約50%で、そのうち約80%は漢方薬を西洋薬的に用い、洋漢総合的使用が18%、漢方専門家2%とのことであった。 したがって、和漢、中医でない「その他」が80%以上ということになる。 後述する予定であるが、漢方薬(エキス剤を含めて)を処方することが漢方診療なのではない。 西洋医学の基礎に立って通常の西洋薬を出すような気持ちで漢方薬を出するは実は漢方診療ではないのである。
さて、”和漢の殿堂” と言うべきところが金匱会診療所である。 殿堂とは言うものの、実は東京駅八重洲口から5分もかからず行ける八重洲一丁目ビル4階にある単なるビル診で、ちなみに1階はメガネドラッグである。このビルの4階に行くと、さすがに漢方薬特有の臭いが立ち込めている。
そもそも金匱会診療所は、「正統派の日本漢方の復興と普及、医師に漢方医学の伝統的手技を習修させるために設立した日本最初の専門機関」 (山田光胤先生曰く) で、現代の日本の漢方の基礎を作られた大塚敬節先生が中心となっての昭和32年の設立で、矢数道明、藤平健といった和漢を代表する先生方が診療に当たっておられた。 もちろん初代所長は大塚敬節先生であった。 今は所長は山田光胤先生で、その他、大塚泰男、松田邦夫等々とわが国の漢方界の重鎮が後進の育成かたがた診療されている。
ちなみに漢方の研究、教育機関として北里研究所付属東洋医学総合研究所は有名であるが、ここの初代所長も大塚敬節先生で、金匱会診療所の方が先に設立されている。 したがって、金匱会診療所は同門の兄貴分的存在なのである。 さらに弟分には渋谷診療所というところもある。
そもそも私が金匱会診療所に学びに行くようになったラッキーなきっかけは一昨年水沢で開催された日本東洋医学会岩手県支部集会の折、特別講演に山田光胤先生が来られた事だった。 会長が桜井先生で、東京医大の同級生という間柄の山田先生がご講演くださった。 内容は基礎的なものだったが、「証」は「症」につながりとのお話はとても印象に残り、早速懇談会でご挨拶にいったところ「漢方でアトピーをやりなさい」とのお言葉を頂いた。
当時の私は、北里研究所東洋医学総合研究所に学んできた皮膚科の同門の者から皮膚科の漢方ということで手ほどきを受けて漢方エキスを使い初めて数年経った頃であった。 ある種の薬は使えて、その効果もある程度は知ってはいるものの、その枠から出られないでいた。 要するに行き詰まっていたのである。 漢方はこの程度のものと高を括っていた。
山田先生にお会いして、一度本物の漢方診療なるものを見たいとの思いにかられて、桜井先生に相談して、ダメでもともとのつもりで手紙を出してみることにした。 間もなくご返事を頂いた。 渋谷診療所で1回だけ見学させて頂くことになった。 平成11年3月8日である。 何の因果か、この3月8日は渋谷駅前のシンボル忠犬ハチ公の命日だった。
金匱会診療所見聞録(2)
『水沢医師会報』2000年5月号掲載より
和漢の源流
山田光胤(てるたね)先生は一年に最大4人しか研修生をとらない。 金匱会診療所と渋谷診療所とそれぞれ2人ずつである。 研修生というよりは弟子と言った方が妥当かもしれない。 何かカリキュラムがあって教えてくれる訳ではなく、唯結々師の技を見よう見真似で盗むのである。 当に職人の世界である。
金匱会診療所に通い始めた頃、今の漢方(和漢)の現状を先生にお聞きしたことがある。師曰く三つの流れを教えてくださった。 一つは大塚敬節一門、京都の細野家、そして千葉大の流れ(藤平健先生など)である。 前の二者のは腹診等よく似ているという。それから関西では漢方専門薬局の伝統が昔からあり、また針灸の伝統は続いていた。 尚、針灸は和漢よりも中医に近い。
たまたま、このようなお話を伺っている頃、山田先生が第10回国際東洋医学会で「東アジア伝統医学に於ける日本漢方」と題してご講演された。 どの内容が日本東洋医学雑誌 第50巻 第2号201~213頁(1999)に掲載されているので興味のある方はご一読頂きたい。 そこに載せられていたのが表1(下記)である。 これでお解りと思うが、和漢は師資相伝の世界なのである。
ここで日本史は苦手、ましてや日本の医学史などはどうでもよいと言われる人の為に極く簡単に日本の漢方医学について触れておく。
和漢と言ってももともとは中国からの輸入医学であるから遣隋使とか遣唐使といった時代に仏教などとともに貴重な先進文化として日本に入ったことから始まる。 もちろん貴重な薬として漢方の生薬も輸入された。 鎌倉、室町時代になると中国との往来も大分安全かつ迅速になり田代三喜という明に留学して本場のトレーニングして帰国した人も登場するようになった
この頃の中国の医学が金元医学(金、元で確立した医学)で、日本では後に後世派と呼ばれた。 なぜ「後世派」かと言えば、江戸時代に鎖国となって、日本独自の発展、中国輸入医学の日本化がなされる過程で、中国医学の原点、古典(主として『傷寒論』紀元200年頃)にかえれとの気運から生まれた流派「古方派」に対する「後世派」だからなのである。 したがって、古方の方が実は新しい流れであって、古方つまり古い方が良いという意味が含まれている。 言わば西洋史のルネッサンスのようなものだと思う。
さて、和漢の確立、中国輸入医学の日本化の成熟は江戸中期、18世紀に頂点を迎える。吉益東洞、和田東郭といった人たちがその代表である。 この時期、一方で杉田玄白らが『解体新書』を著わすなど西洋医学、即ち「蘭方」も日本に入って来ており、それに対しての中国系医学が「漢方」なのである。 現代の西洋医学にせよ漢方医学にせよ輸入医学である。 しかし、和漢は中国輸入医学を日本人向けに日本人独特の器用さによって見事に日本化し、輸入元の中国とはまた一味違った医療なのである。 ちなみに現代中国の伝統医学-中医は、金元流の伝統が引き継がれ、その延長線上に位置づけられているとのことである。
日本の漢方は、後世派、古方派の二流派と、両派を合せた折衷派に分かれて明治時代となった。 明治政府が西洋医学のみを医学としたため、漢方は非合法な医学とされてしまった。 20世紀になって西洋医学を学んで医者となった者が個人の興味で和漢の師に学んで今日に至っている。 特に関東では大塚敬節、矢数道明、関西では細野史郎等の諸先生が中心となって戦前戦後にかけて和漢の復興に努力されたとのこと。 因みに山田先生は、幼少の頃病気がちのところを大塚先生に命を救われ、学生の頃すでに大塚先生のご指導を受けて、大塚先生のご令嬢とご結婚され、さらにご子息も金匱会診療所で診療に従事されておられる。
山田先生の門下生「山友会」として50数名を数え、私も遂にその末席に加えて頂いた。 何んと古方派の正統中の正統の流れに入れて頂くこととなってしまったのだった。
金匱会診療所見聞録(3)
『水沢医師会報』2000年6月号掲載より
腹診の妙
和漢を特徴づける大きな特色として、「腹診」がある。 この腹診によって「腹証」という患者の身心の個性、状態が把えられるのである。 中医学にはこれがない。 因みに大塚敬節先生の著書に「日本で腹診術が発達したのは、日本の婦人には貞操観念がないので、男の前でも平然として腹を診せるがためであり、中国で腹診が発達しないのは、中国婦人は貞操堅固で容易に腹をみせないためであるとあり、私は唖然とした。」(『漢方医学』)との腹診に対する中医の対応が載せられている。 貞操観念の真偽はともかく、それぞれの国の風習や文化が関係しているのだろう。
もともと『傷寒論』の時代(紀元200年頃)の中国医学には腹診術はあったらしく、わが国のルネッサンス期にあたる江戸時代に日本で復活したというわけである。 その最大の功労者が吉益東洞(1702-1773)ということである。 腹診はそもそも按腹というマッサージでもあったらしい。
さて、昨年2月頃、山田光胤先生に手紙を出していた頃のことである。 和漢の診察について何も知らないで和漢の大家のもとにお邪魔するのも気が引けて、本を頼り何はともあれ患者さんのお腹を触って診た時期があった。 西洋医学の触診すらすることのほとんどない皮膚科医にとっては、本当に新鮮な体験であった。 肝臓とか脾臓とかを触れるのでなく、お腹を全体的に触れてみる。 大きなお腹や軟らかいお腹、部分的に硬くなっている処があったりもする。 このようなのを胸脇苦満と言うのだろうか、これが腹直筋の緊張なのだろうか、はたまた、振水音と言うけれど本当にポチャポチャとお腹から聞こえてくるのだろうか-患者さん毎にそれぞれ違っていた。 和漢の診察法(「術」と言った方が良いかもしれない)を知りたいとの気持ちがどんどん強くなってくるばかりだった。
いよいよ和漢の大家、山田光胤先生の診察に同席することを許された日のことである。 診察の前に、まず私の手を取られて冷たくないか確認された。 そして初心者なのだから勝手に患者の身体に触れないこと、触れるときは患者に苦痛を与えないことなどのご注意を受けた。 確かに腹診とは、いわばツボを押すようなもので、少し力を入れ過ぎると患者にとってかなりの苦痛となるのである。 逆にやさしく、なでるように押す(按圧する)とマッサージのように気持ちのよいものともなる。
簡単な問診を終えた先生は、ベッドの上に膝を伸ばしたまま(西洋医学の触診のように膝を曲げない!)横になった患者を前にして、まず脈を診られた後、いよいよ腹診となる。 腹部全体を撫でるように触れられたあと、上腹部で胸脇苦満の有無、心下部の硬さ、腹直筋の状態を診られて、臍部を中心に拍動を診られてから下腹部へ。 下腹部では瘀血の有無や小腹不仁の有無を調べられて、最後に振水音が聞えるか手で下腹部から上腹部へ軽く叩かれた。 これらの動作の間、胃下垂の有無をわれわれに教えてくださった。 動悸のある患者さんであれば胸に手掌を当てられて心臓の大きさを示してくださった
そして師曰く「手で感じられるように訓練しなさい!」と励ましてくださった。 この間患者一人あたり10分間程の診察であった。
山田先生は、『漢方の診察と治療・基礎編』という大部分を腹診についてのことが記されている本を執筆され、また、『漢方製剤活用の手引き』というポケット・ブックでは各漢方製剤毎の腹証を監修されるなどされておられる。 入門してわかったことであったが、山田先生は当に“腹診の神様”とお呼びしていいくらいの方だったのである。
実際にこの腹診を用いて非常に診察の幅が拡まった。 もともと私の学んだ皮膚科学は全身を考えた西山皮膚科学で、西山茂夫先生より折に触れ病名をつけることよりも何故その皮膚症状がおこったかを考えなさいと教示された。 これまでの日常診療でも、できる限り全身的観察を念頭に置いて進めてきて、若年性の再生不良性貧血の女性や悪性リンパ腫の老人などを専門医に紹介することができた。 しかし発疹のみで全身を把握することは、実に難しい。 軽微な異常、全身的なアンバランスといったものは血液検査にすら異常値として顕れないことすらある。 ところが腹証や脈証といった漢方的診察では、この身体的調和の歪みとも言うべきものを瞬時に把えられることもあるのである。治療道具としての漢方薬を使うか否かにかかわらず、便利な診察技術なのである。 もちろん漢方薬を選択するのに抜群の威力を発揮する!
ここまで腹診のいい事ばかり書いてきたが、実は大きな悩みもある。 一つは診察時間が長くなることである。 今まで発疹に関係することだけ聞いて、皮膚を丹念に見て、必要とあらば簡単な検査をすれば一応は終わっていたものが、皮膚以外の便秘の事やら生理に関連する事、はたまた、口渇の有無なども聞いてから腹診に辿り着くのである。 とても3分間診療などは夢のまた夢、周囲の職員はブーブーである。 最近ではどうしても腹診の必要な人だけに行うことにしている。 しかし一年間の腹診の蓄積は今考えても決して無駄ではなかったと思う。
次に問題なのは皮膚科でお腹を触るということである。 内科、外科の一般診療でお腹を診たり触れたりするのは当り前の行為であるが、皮膚科で、まして腹部に発疹すらないとなると話は別となる。 おそらく本医師会会員の中にも岩崎は何か得体の知れない診察をしているらしいくらいに思われた先生もおられるかもしれない。私自身患者さんの為と思ってやったことではあるが、今にして考えれば、患者さんの戸惑いたるや察して余りあるものがある。 皆がやっていないことをやるのは結構労力がいるものだと思う。
漢方の診察法は4つに大別され四診という。 望診、聞診、問診そして切診の4つである。 腹診は、脈診と伴に、医師が患者の身体に直接触れる切診(せっしん)に含まれる。 即ち切診とは「接身」であるが、その意味するところは「接心」にも通じ、できることであれば「摂心」でもありたいと思う。 漢方にあっては肉体と精神は一体的なものであるからだ。和漢を学んだものにとっては何でもない当然の行為であっても、多くの大学に講座すらない分野であってみれば、大部分の医師、特に細分化した部分しか診る機会のない専門科目にあっては、なかなか理解し難い診療であると思う。 当の私自身もついに20ヶ月前まで全く考えてもみなかった世界なのだから・・・。
金匱会診療所見聞録(4)
『水沢医師会報』2000年7月号掲載より
漢方エキス剤あれこれ
漢方治療は漢方薬を処方することとイコールではない。 しかし、漢方薬をぬきにしてその治療は成り立たない。特にわが国では、漢方薬と言えば、漢方製剤(エキス剤)を意味していると言えるくらいにエキス剤が一般化している。 そして、それには番号がついていて、本来の方剤の名称よりも番号の方が幅を効かしているくらいだ。
さて、この番号、だれがつけて、何を意味しているのか、お考えになった方はおられるだろうか。 その答えが金匱会診療所にあったのである。 金匱会診療所の薬剤部長である小根山隆祥先生がこの番号の名付け親なのである。 こんなにも番号が一人歩きするとは思っても見なかったそうである。
小根山先生がツムラでエキス剤の研究開発をされていた頃、すでに小太郎製薬によって1~6番までのエキス剤はできていたそうである。 当初ツムラでは婦人薬として中将湯があって、その錠剤化したラムールをもっていた(因みに、浴用中将湯がバスクリンにつながっている。)。 この技術を応用発展させていったとのこと。 7番には八味地黄丸、8~12番まで柴胡剤が続き、小柴胡湯に近い関係にある半夏瀉心湯(小柴胡湯の柴胡と生姜を黄連と乾姜に替えて)が14番、16~21番までは茯苓などを含む利水剤関係が続きと言う具合にある程度の脈絡はあるのだが、最も大切だったことは許認可の問題だったようである。 当時、工場が静岡県藤枝市にあって県の製造許可が何んと言っても重要だったそうである。 それでまず書類上、書類の作製しやすさ、許可の受けやすさが重視され、そのために構成生薬が似たものが優先されたこともあったとか
一挙に何剤もの許可申請を行おうとしたところ、少しずつ持って来るように指示されたとか。 日本にあってはまず役所の壁をクリアすることが第一のようである。
次に問題なのが使用頻度である。 これはツムラとの関係が深かった大塚敬節先生の意見が大きかったようである。 もともと金匱会診療所の前身は医療法人社団金匱会中将湯ビル診療所としてツムラの中将湯ビル内にあった。 また大塚先生が臨終に当たって駆け付けたのは、身内を除いて矢数道明、武見太郎、津村重舎(初代)の三氏だったとのことである。 金匱会診療所の創立にも津村重舎氏が一役買っており、この診療所とツムラとの深い関係にあるようである。
大塚先生は、単に使用頻度のみならず、使い分けのことも考えられてアドバイスされたそうである。 小根山先生が和漢にない中医の漢方薬についてご意見を伺ったところ、「そんなものは漢方じゃない」と言われたこともあったそうである 中医では生薬の寄せ集めとして一つの方剤が処方され、患者一人一人について生薬の分量や種類が違ってくる。 一方、和漢では「傷寒論」を始めとする出典に基づいた方剤の使い方を重視する。 したがって、エキス剤が作られる発想や土壌は和漢ならではのものである。 このエキス剤は技術的な問題もさることながら、考え方の出発点から和漢独特のもので、わが国の発明品なのである。 実際、若き日の山田光胤先生も漢方製剤を作る実験をされたこともあったとお聞きしたことがある。 また、金匱会診療所の弟分的施設である渋谷診療所は、そこでの大半がエキス剤で処方されている
前者が自由診療で生薬として漢方薬が処方されるのに対し、後者は保険診療でエキス剤主体に治療が行われている。 これは単に患者の便宜をはかる為だけでなく、エキス剤が漢方治療としてどれだけ使えるかを試す目的もあって設立された旨を山田先生からお聞きしたことがある。 このようにエキス剤誕生には和漢なしではありえなかったと言ってもいい。
最後に開発しやすさということを問題にされた。 エキス剤といっても小太郎、ツムラ、カネボウ等々数社で作られているが、各メーカー毎に製法が違っているらしい。 小根山先生たちには、ちょうど傘に雨が落ちるときに傘を回転させると滴が均一に飛んでいくように、抽出した濃縮液を回転した板の上に落として瞬間的に加熱乾燥させて一度板状(ちょうどチョコレートの板のよう)にしてから砕いて粉にしていたとか。 製品の安定性をまず重視したと言っておられた。 また、生薬の単味ではエキス剤はできず、複数の生薬で方剤として混ぜて作ることによって有効成分が抽出されやすくなってエキスが出きやすくなるのだという。 たとえば延胡索という生薬を単味で作ろうとするとゲル状になってしまうのだそうだ。 生薬の複合した方剤とは、合わせて作るところに意味があるということである。
今回は漢方製剤(エキス剤)について和漢との関係で述べたが、その番号と同じようにエキス剤自体も薬として一人歩きしているように思う。 それぞれの医師や薬剤師が各々の用い方でエキス剤を患者に投与している。 おそらくその大部分は西洋薬と同じような感覚で使用されていることと思う。 それはそれで新たなエキス剤の存在意義が見い出されていくのかもしれない。 しかし、和漢を学んで思うことは、その根本的なところを理解していると、エキス剤の使用法にしてもより拡げられた視野で使っていけるということである。 今や私の日常診療にあって、漢方エキス剤は治療道具としてなくてはならないものになってしまった。
金匱会診療所見聞録(5)
『水沢医師会報』2000年10月号掲載より
第1回山友会学術懇談会に参加して
去る9月15日、和漢の大家・山田照胤先生の門下生の会(山友会)の第1回山友会学術懇談会が開催された。 新参者である私にも案内状が来たので顔を出してみることにした。 懇談会とは名ばかりで、ちょっとした学会並の演題が8題続き、最後は山田先生の教育講演で閉会となった。 参加者は50数名にわたり、北は青森から南は九州に及ぶ。 演者も然りである。 会場も東京駅八重洲北口大丸デパートの中とあって全国から集まるには調度良いところだった。 かく言う自分も好都合な場所で日帰り可能だったので参加させて頂いた訳である。
さて、「開会の辞」の中で、山友会の会長でもある山田先生は次のように述べてあられた。 漢方薬は広く使われるようになっているが、果たして正しく使われているのか。 振り返れば日本の漢方は明治政府の政策で明治末には省りみられなくなり、細々と残っていた流れとして明治の和田啓十郎先生、大正時代の湯本求真先生が古方の和漢を復元され、それを大塚敬節先生が受け継いで現代の漢方のもとになっている。 もう一つは、京都の細野史郎先生が明治の大家、浅田宗伯先生の脈承をわずかに残しているのみである。 われわれは、日本の医術を正しく学んだ僅かな者として、湯本-大塚流の漢方を研究というよりも日常の診療に生かしていきたい-と。
考えてみれば、今の日本にあって、なかなか本格的に漢方を学べる機会はない。 日本の大学の医学部で漢方講座があるのは、ほんの数ヵ所である。 先般、医学講演会で水沢に来られた田代眞一教授(昭和薬科大学、講演内容は本会報7月号に掲載)も懇談の時に話しておられたが、薬学部にあっても西洋薬の原料としての生薬の講義はあっても漢方薬としてのものはないとか。 したがって巷の薬局に漢方薬とくにエキス剤を並べているところは多いが、きちっと漢方薬について学んでいる薬剤師は皆無に等しいと言う。 私もまだまだ初学者とは言え、日本の医術を正しく学ぶ僅かな者の端クレに加えて頂けたことだけでも感謝に絶えない。
参加したメンバーは、もともと内科の先生が多いが、外科、小児科、整形外科等々出身も多彩で、山田先生も精神科の医師として数年診療されておられた時期がある。 因みに今回の教育講演のテーマは「アトピー性皮膚炎の漢方治療」で、皮膚症状に対する漢方治療も先生の得意とする分野である。 御陰で私も随分助かっている。 もとより漢方には西洋医学的な臓器別の細分化などはないのであって、心の問題を含めて全身的に診るのが漢方の真骨頂である。 もっとも西洋医学を一度は学んできたものが改めて和漢を学び直すのであるから、もともとの西洋医学的専門が付いて回るのは当然である。 逆に、このような会では西洋医学的に専門分化した医者が、山田流和漢というまったく別の共通点で情報を交換し合うところに意義があるように思う。
私が始めて山田流漢方に触れたとき、ある種のカルチャー・ショックさえ覚えた。 今まで学んできた西洋医学とは別な体系、治療術があることを知ったときの感動は新鮮だった。 これしかないと思っていたものに、別の世界がもう一つあったのである。 そんなことを閉会後の懇親会である先生にお話ししたところ、同じ大塚敬節門下でも山田先生と寺師睦宗先生とでは流儀がまた違うと言うことだった。
山田先生も今年喜寿ということであるが、今も現役で一線に立って私のような初学者の教育もしてくださっている。 漢方の世界では老いれば老いるほど経験を積んで術に磨きがかかって味が出てくる。 弟子からも尊敬され大切にされる。
かつて私が病理学教室の大学院生でいた頃、隣の教室の教授が「退官後の教授ほどみじめなものはないよ」とポツリと話されたことを思い出す。 事実、私が病理で師事した小島瑞先生は網内系病理の権威で、弟子を何人も教授にした大病理学者であったが、亡くなられた直後に水沢から水戸のご自宅に駆けつけてみたら家族の他は僅か数人の弟子の先生が細々と葬儀の計画を立てていた。 往年の大先生にしては寂しい光景だった。 筑波大学教授を退官されて10年程経ち第一線から退いて数年になっていた頃だったろうか、先生のご専門がここ20~30年で激しく変化し、すでに「網内系」という言葉は歴史的な意味しか持たない死語となっていることも関係しているからだろうか。 いずれにせよ、西洋医学では常に古いものは新しいものに取って代わっていくのである。
古いものを尊ぶ世界では、ともすると権威主義的になりやすい部分もあり、一概に手離しで歓迎できないこともある。 しかし、苦労して積み上げた経験には最新の知識でも適わないところもある。 最新の情報はそれとして生かしていくことは大切だと思うが、情報に振り回されることなく自分の経験の術に磨きをかけることも大切だと思う。
西洋医学的知識を生かしながら、一方で西洋医学ではどうにもならない患者にも和漢の磨かれた術による救いの手がさし伸べられるようになれるのが今の私の理想である。
金匱会診療所見聞録(6)
『水沢医師会報』2000年11月号掲載より
口訣について
最近、私の手元に送られてきた山友会(山田光胤先生の友の会)の会報に山田先生の次のような一文が載せられていた。 「漢方という医術は、古武道や古典芸術などにも似て、最終的には師匠の口伝や術技の見習いによらなければ分からないところがあります。」-と。
『広辞苑』によると「口伝」とは「奥儀などの秘密を、口伝えに教え授けること。」とある。 また和漢では「口訣(くけつ、こうけつ)」と言う言葉がよく使われ、これも調べてみると「口で授ける秘訣。文書に記さず、直接に言い伝える秘伝。」とある。 たとえば、江戸末期から明治中期に活躍した漢方医、浅田宗伯(1814-1894)の常用処方をまとめたものに『勿誤薬室方函口訣(ふつごやくしつほうかんけつ)』があるが、要するに浅田大先生から教えられた漢方薬の使い方のコツを古人の説と先生自身の経験とを合わせて弟子に伝授したものをその弟子が成書としてまとめたわけである。
山田先生の著書『図説・東洋医学 湯液編Ⅱ』の中に、漢方近代化の流れは、昭和7年に、南山堂から『漢方診療の実際』(初版)を発行させて、一つの完成をみた。 この書は、大塚敬節、矢数道明、木村長久の3医師と、薬学者清水藤太郎の共著であって、現代医学的病名に対して、漢方薬を用いる方法を述べた最初であり、しかもそのような使用法を、ほぼ網羅している。
さらに、共著者の3医師は、古方派、後世派、折衷派それぞれの学統を継ぐ学者であった。 したがって、この書は、江戸時代以来の漢方医学の諸流派を総合したことになる。
近年、漢方薬を医療に応用する医師が急増して、現代医学の病名によって漢方薬を用いる機会が多くなった。 しかし、その用い方の起源が、この書『漢方診療の実際』(改訂版・昭29年)にあることを知る人はあまりないのではなかろうか。 この書以後さらに、同じ共著の『漢方診療医典』が昭和44年に発行されたとはいえ、このような漢方薬の用い方について敷衍されたものは、決して多くはない。
『漢方診療の実際』は、江戸時代中期以降、古方派の医師達が指向した、漢方の科学性の一つの到達点ともいえよう。 とある。 今手に入るのは『漢方診療医典(南山堂)』であるが、ちまたに氾濫している漢方エキス剤の使い方の原点はこれにあると言って過言ではない。言わば現代風の口訣集である。 このように和漢では経験の蓄積を重視し、師弟関係の中から術を積み磨いていくのである。
そもそも今、自分達が受けてきた学校制度を基礎とした教育は明治時代に欧米から輸入されてきたもので古くから日本にあったものではない。 和漢が成熟した江戸時代には医療は医学というより医術であって、師弟関係にあって発展し受け継がれたのである。 如何せん明治政府によって本来日本にあった医術=和漢は否定され、衰退の一途ることになる。
このように書いていくと師弟関係が和漢の専売特許のような感じがするが、私の医学部卒業後の進路では、本当に良い恩師に恵まれた。 病理学教室に5年間在籍し研究めいたこともさせて頂いた。 ワン・ツー・マンで顕微鏡を覗き込みながら何十枚の標本を見ながらデスカッションをしたり、バシバシ撮った電顕写真を一枚一枚細かくその判読方法をトレーニングして頂いたり。 少し寝不足の時、長時間顕微鏡を見ていて気持ち悪くなってしまい早退したことも今となってはいい思い出である。
皮膚科になってからも皮診の見方考え方を事細かく指導して頂いた。 いずれの分野も形態学的要素が強いので、どうしても実際の症例の中でニュアンスを掴んでいくしかなかった。 こんな経験のうちで達した結論は、ズバリ!いい師に巡り合わないといい弟子はよほどの事がない限り育たない!! -である。 シドニー・オリンピックの高橋尚子選手も然りだけれど、優秀な監督がいて、良いコーチ、良いスタッフがいて、一流の選手が生まれるのである。 逆を言えば、出来の悪い指導者のもとでいくらがんばっても凡人ではなかなか芽は出て来ない。
洋の東西を問わず人間関係、運命を左右する大きな要素の一つは縁である。 幸い私自身の周りは水沢医師会会員の諸先生を含めて良縁に恵まれている。 あとは自分の努力次第か!?
金匱会診療所見聞録(7)
『水沢医師会報』2001年 2月号掲載より
ついに21世紀を迎えた。 金匱会診療所に学ぶようになってから3年目となった。 最近になってやっと脈証のいろはがわかってきた。 腹証もそこそこに見えてきたところか。 和漢とくに古方の流れは伝授される部分が多く、一歩一歩年月を重ねて身につけていくと云う感がある。 道具としての漢方薬の使い方にしても同じである。 一つ一つの方剤の特長をコツコツと噛みしめていくといったところだ。
さて、平成12年には結構、岩手県内で漢方に関する講演会が開催された。 そのいくつかへ聞きに行くことができた。講演された先生方は第一線で活躍される著名な方々で、私のような未熟者がとやかく言えるものではないが、今の自分を書き記しておく意味で、自分史的な観点から感想を留めておこうと思う。
まずは、2月27日盛岡での広瀬滋之先生のお話。 『症例から学ぶ漢方診療の実際』ということで、脈証や腹証などの和漢的診療方法とそれらに基づいた代表的方剤の実際的な用い方の、力強くバイタリティに満ちたユーモアたっぷりの講義であった。 経歴を見ると聖光園細野診療所の名があり、古方の流れ(月報433号5頁参照)であることがわかる。 自家製テキストに加えて先生の医院で配布しているパンフレットも頂戴したが、実際の診療では漢方に限らず、ご自分が良さそうと思うことは何でもやってみている風が感じとれる。 特にアトピー性皮膚炎については大分立派なパンフレットを作られておられ、外用にもステロイド剤の他にも、丹羽軟膏(実は皮膚科専門医の間では評判が悪い軟膏)も使っておられるようだ。
次に第22回水沢漢方懇談会の田代眞一教授(昭和薬科大)。 講演前後の時間でお話をお聞きしたが、とても人当たりの良い先生だった。 薬学出身だけあって漢方薬の薬理的面を研究されている訳であるが、普段お話をお聴きする臨床漢方医の先生とはまた一味違った面に触れることができた。漢方薬も科学的裏づけが少しずつされているようである。
10月21日には花巻で第5回東洋医学会岩手県部会学術集会が行なわれ、特別講演に“経方理論”で有名な江部洋一朗先生の話を聴くことができた。 江部先生は中医系の漢方であり、演題もズバリ『経方理論の初歩』である。 和漢の先生が実際的漢方薬の運用方法の講演が多いのに対し、江部先生のお話は理論的な話が多く、本当なのだかどうか、いろいろな分野のいい所取りのようで、最後は和漢の専売特許である腹診にまで触れられ「簡単だから皆さんもやってみてください」との言葉には少々ア然とした。 ともあれ理論的なことが好きな先生方にとっては結構魅力的であったのかも知れない。
最後は、やはり花巻で開催された小田島漢方講演会(11月18日)である。 『即効が漢方』との演題で大田黒義郎先生が講師であった。先生は大阪の開業医で、大阪弁の漫談風のしゃべりで時間の経つのも速かった。 大田黒先生はエキス剤派で、漢方の第一人者の話や著書が概して生薬を念頭にしたものが多いのに対して、先生の話はエキス剤一色であった。 エキス剤に居直って、エキス剤ならではの使用がシャベリと共に楽しく聴けた。 逆に言えば、今後はエキス剤世代がエキス剤の漢方として一つの分野が築かれていくのではないかと思ったほどである。 とは言うものの腹診が大切で、忙しくとも腹診をするようにとの言葉は印象的であった。こうして四氏の講演会の印象を漠然と書いてみたのであるが、4人が4人とも別々の“漢方”を話されているのが興味深い。 ハードとしての漢方薬はおそらく同じような薬を使われておられると思うが、その運用のソフト面は大分違っているようである。 いろいろな観点から漢方が把えられ、様々な角度から実際に漢方薬が用いられているということなのだろう。自分がその一つの観点にドカッと腰を置いてみればみるほど様々な面が読み取れてくるのがおもしろい。
もう一つ、自分が皮膚科医であるということから一言。 このような講演の中に必ずと言っていいほど皮膚病、特にアトピー性皮膚炎が取り上げられているということである。 実際、金匱会診療所の山田先生の患者にもアトピー性皮膚炎の患者さんが何人かおられる。 アトピー性皮膚炎のような慢性疾患に関して皮膚科医の手を離れ漢方治療に走る患者さんが結構いるのである。 西洋医学的病名では病名が決まると薬もだいたい決まってしまう。 同系列の薬がいくつかあって、それを取っ替え引っ替えしているうちはいいが、そのうちに駒切れになってしまう。 勢い長い期間患者の症状の如何にかかわらず同じ薬が長い間投与され続けることになる。
まして、皮膚科のように患者数をこなす必要のある科は一人当たりの診察時間も流行れば流行るほどどんどん短縮されてしまうのが現状である。 そんな中で医者への信頼が失われて行くのだろうか。
今やっと漢方薬をどうにかこうにか使いこなせるようになって、体質改善ということも含めて漢方的な全身状態に配慮した処方がなんとか出来るようになってきた。 患者さんの信頼を決して裏切らないように、充分に納得して頂ける医療を目指して、21世紀も自分なりにガンバッてみたいと思う。
金匱会診療所見聞録(8)
『水沢医師会報』2001年 4月号掲載より
縁あっての漢方
去る3月10日、新宿にて漢方の師である山田光胤(てるたね)先生の喜寿を祝う会が行われた。山田先生は桜井昭彦先生と東京医大の同級生であるが、年齢は大分上である。 会でのご挨拶でも話されておられたが、小さい頃に大病されたためである。
小学校の頃、学校でボール遊びをしていたところ、強くボールが当たったのをきっかけで腹膜炎になり、慢性腹膜炎と診断され、西洋医学では治らず、和漢の大家・大塚敬節先生に廻合い「漢方医学で命を救われた」(山田先生の口ぐせ)とのことである。 お腹が痛くならなければ家にいても何もすることがないので学校に行っていたそうであるが、お腹はパンパンの腹水が溜まった状態で、旧制中学の入学試験では健康診断の段階で「君はもう帰っていいよ」と先生に言われて試験も受けられなかったとのこと。 病気が良くなって二年遅れで旧制中学に入学。 昭和十八年に旧制中学を卒業されたが、春の大学の試験には落ちたため、秋に試験のあった陸士に入校された。 2年後に終戦を迎えることになったが、同じ年齢の人たちはほとんど戦死してしまったそうである。 「病気のおかげで命拾いをした」との言であった。 戦後、大塚先生の勧めもあって医学を志されたが、学生時代から大塚先生の漢方の手ほどきを受けられたそうである。 「漢方を勉強するのにも若いうちでないとダメだな」とも良く口にされる言葉である。
尚、慢性腹膜炎と言えば当時とすれば結核性が多かったわけだが、菌は結局見つからずアレルギー反応だったのか-とのことである。
喜寿を祝う会の〆の言葉を述べられたのは渋谷診療所(会報No.432号「金匱会診療所見聞録(1)」参照)の現在の所長、岸 篤先生であった。 先生はもともと産婦人科医師で手術の折、ウイルス性肝炎に感染され、東京医大に8ヶ月入院しても良くならず、どうしようもなくて山田先生の漢方治療を受けられ、治ってしまい、漢方の道に入られたとのこと。 岸先生は山田先生と東京医大の同級生で、したがって桜井先生とも同級生ということになるので、初対面であったが挨拶することにした。岸先生のお父様も医者で、桜井先生が東京医大の放射線科にいた頃、放射線科の教授に頼まれて岸先生のお父様の学位論文作成の手助けをされたこともあったとか。 人間関係とはいろいろと繋がっているものである。
繋がっていると言えば、今現在、桜井医院が建っている土地は、もともと漢方医(江戸時代の医者の大部分が漢方医なのだが)が開院していたところだそうである。 私自身も桜井先生のご縁で山田先生を師と仰ぐようになった訳だが、何となく見えない糸で和漢と繋がっていたような気がする。
もともと大学を卒業して、病気の理法を知りたくて病理学教室に飛び込んだ。 病理解剖や組織検査、電子顕微鏡の世界や免疫組織化学的研究をやってミクロへミクロへと進んだところで皮膚科医となった。 皮膚科医となって、恩師、西山茂夫先生より「皮膚を通して全身を診よ!」と指導されてはいたものの、本当の意味での全身を診るところに立っていなかったような気がする。 皮疹を診て、全身疾患や内臓病変が疑われるときには尿検査や血液検査を必要に応じて行ってはいるものの、やはり身体の中に起こっていることの、ほんの一部の変化しか観ていないからである。
今、縁あって漢方、とりわけ和漢を学べる機会を得て、真に全身(心を含めて)を診る術に廻合えた実感がある。 ミクロから出発してマクロにも到達できたのである。 とは言うものの、腹証のイロハを体得し、脈証の感どころを掴むのにまる2年かかった。 漢方の診察法を把んで、漢方薬を自由自在に駆使するにはもう少し時間が必要のようだ。
金匱会診療所見聞録(9)
『水沢医師会報』2001年 5月号掲載より
かぜ一つとってみても・・・・
前回も触れたが、私の和漢の師である山田光胤先生は学童期に大病をされて、漢方の大家・大塚敬節先生によって命を救われたとのこと。 また現在の渋谷診療所の所長である岸篤先生も肝炎で苦しんでいたところを山田先生の漢方治療で救われた話も前回述べた。 山田先生の喜寿の会でお会いした髙木嘉子先生は、今や冷えの漢方治療で有名になりつつあるが、この髙木先生もお若い頃大へんな冷え症で漢方治療によって健康になったとのこと。 このように漢方にのめり込んでいった先生には、漢方治療によって健康を得たというエピソードをお持ちの方が多い。
自分についていえば、縁あって漢方薬エキス剤を使うようになった10年前頃には、カゼを引いて葛根湯を数日飲んで胃をこわしてみたり、鼻水と言えば小青竜湯を飲んで下痢してみたりと素人療法からのスタートであった。 3年前に山田先生にご教示を頂くようになって、見様見真似で漢方薬を使うようになり、腹証を習い脈証がやっとわかるようになって、最近ようやく『傷寒論』の有名な陰陽、寒熱(三陰三陽)といった病状による病期のことや、闘病反応の個人差を示す虚実、病気の進行度(病位)を意味する表裏のことが理解できるようになって、漢方の良さをしみじみ感じられるようになった。
たとえば私のカゼの引きはじめは、寒気がしてクシャミが出て、やたらと鼻水がでるようになって咽頭痛が出てくる。 高い熱を出すことはないが、だらだらとすっきりしない状態が続いて、ときに咳き込むようになる。 今考えれば虚証のカゼの引き方そのもので「少陰の直中」と言われるものに近い反応であったわけである。 実際、私の脈は沈小で、腹診でも胃内停水や腹直筋の緊張がみられるなど虚証の腹証がみられ、軽度の小腹不仁といった老化現象も確かに顕れはじめている。 このような体質に葛根湯や小青竜湯では胃腸をやられるのは当り前のことなのだ。 その当り前さをわかるまでの和漢的常識を身につけるのに時間がかかる。 はっきり言えば山田先生のような師に実際についてみないと、本を読んだり講演を聞いたりだけでは和漢は身についてこない気がする。
漢方ではカゼ一つとってみても病期や体質、病期の進行度によって使う薬が変わってくる。 またその変化について実に事細かく記載されており、なにがなんだか、どこがどう違うのか最近になってやっと区別ができるようになったくらいだ。
特に和漢では症例集的な著書も多く、こんな時にはこんな薬、こんな状況ではこんな対応が大切といった具合であるが著者によってもことなり、とても覚え切れるものではない。和漢の大家・大塚敬節先生が「漢方医学を研究せんとする人のために」とのことで次の5項目を挙げている。 ⑴志を立てること ⑵白紙になって漢方と取り組め ⑶散木になるな ⑷師匠につくこと ⑸読むべき書物-『傷寒論』『金匱要略』。 なるほどと身にしみて感じ入っている次第である。
金匱会診療所見聞録(10)
『水沢医師会報』2001年 6月号掲載より
桜井医院が院外処方となった訳
去る5月11日わが桜井医院では院外処方を始めた。
そもそも院外処方は患者さんの立場に立ってみるとあまり良いものとは思えない。病医院の会計で待たされ、院外の薬局に足をわざわざ運びながら待たされ、さらにトータルで高くなる医療費を払わされる。 薬局の薬剤師さんが、いつもニコニコとやさしく薬の説明や飲み方などを病医院の院内薬局以上に気を配って教えてくれるのであればまだしも、出来合いの長ったらしい説明書を、たかがカラーだからと言って是見よがしに渡されて事務的に扱われたらたまったものではない。 数分前に受けた医者の注意とわざわざ足を運んで聴いた薬剤師の説明とが違ってでもしたらどちらを信じていいのやら病気の他に悩みがもう一つ増えそうな気がする。
ここ数年の院外薬局の推進の音頭も、病医院についてみれば、薬価差益ゼロ時代となって経理の簡素化や人員削減など病医院の経営上のメリットが強調され、患者にとってどうなのかは、薬の専門家である薬剤師が説明するのだからという分業による理想像のみが語られるだけで、二の次にされている感がある。 「医薬分業」が語られるときの薬剤師は、薬を知りつくしたスーパー薬剤師が突然と空から降ってくるかの如くに登場してくるようだ。
このような現実を心配しつつも何故桜井医院は院外薬局に踏み切ったのか? この4月からの県立病院、当地にあっては胆沢病院の全面院外薬局化に同調したのだろうか?
実は漢方薬に大きな理由があったのである。 私のように皮膚科治療に当たって通常の治療もやり尚且漢方治療も加えていくとなるとどんどん使う薬の種類が増えてくる。「皮膚病の漢方薬」というような大ざっぱな病名処方で十味敗毒湯や消風散、当帰飲子などを出している間はいいが、だんだん本格的になってくると「皮膚科」の枠組みはほとんど意味がなくなってくる。 皮膚はあくまでも全身の一部であって、全身の中に皮膚がある。 皮膚の健康は全身の健康あってのもので、また皮膚の異変は全身的な異変の徴候とも言えるからだ。 この様に把えていくとあらゆる漢方薬が使う選択肢に入ってくる。 たとえば一般的なめまいの薬や胃腸薬が直接的あるいは間接的に皮膚に効いてくる可能性がある。 このあらゆる可能性を絞り込むために、脈証や腹証が大いに役立ってくる。 これが「証の診断」とか「随証処方」とか言われる漢方独自の方法論の醍醐味でもある。
和漢の醍醐味に浸るほどの技量はまだまだないが、あらゆる可能性を少しずつ経験してみたいという欲求は、学べば学ほど大きくなってくる。 また使ってみてなるほどと得心できることも多い。 こうなってくると増々薬の量が多くなってくる。
もう一つ薬の多くなる理由がある。 剤型の問題である。 今や“飲食の時代”。 「良薬口に苦し。」という訳にはなかなかいかない。 漢方薬と言っても方剤によって味が違うが、とりわけ皮膚病関連とされるものは苦いものが目立つ。 人というのは最初が肝腎で、一度嫌な思いをすると次が続かなくなってしまう。 したがって、できるだけ口当たりが良さそうな方剤から選ぶ必要も出てくる。 証が合えば苦い薬も苦と感じることなく口にできるとは言われているが、自分のような未熟者では最初から証を百発百中、すべからずジャスト・フィットさせるだけの自信はない。 さらにはエキス剤にしたところで粉末は最初から受けつけないとする若い人も結構多い。 そこで漢方エキス剤の錠剤やカプセルのものも用意したくなる。 そんなこんなで薬の種類(剤型別も含めて)は増える一方となる。
こうなってくると診療所の小さな薬局ではとても収納・管理できる薬の数ではなくなってしまう。 況してや薬の保管・管理については厳しくなる時代である。 いっそ薬局は外へとなって院外処方に至ったのである。
院外処方となって改めて漢方薬を広く勉強し直しての最近の診療である。 この薬も使えそうだ、あの薬はどうかと診療の楽しみがまた一つ増えたような気がする。
先日、やはり院外処方をしている神奈川で皮膚科を開業している後輩に、いままで述べてきた話をしたら「先生、そんなにいろいろと薬を置いている調剤薬局なんかありませんヨ!!」と言われてしまった。 何しろ東北地方ではまず他に使っていないような漢方エキス剤も含まれているので彼の言うことは至極もっともな言葉であった。 当胆江地区でもまだ皮膚科の院外処方は珍しく調剤薬局泣かせでマークされるかもしれない。 医薬分業の理想の“面分業”などは、私にとっては当てはまりそうにないのが現実である。 だからこそ、門前薬局で何が悪い!!-と言いたくなる。
原点に帰って「患者の為の医療」という立場からすると、院外処方のデメリットを越えたメリットを大きくすることしか手はない。即ち、私自身の医療の質の向上が最も重大とのプレッシャーを自らにかけているところだ。