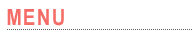一口メモ
My Portrait
『奥州市医師会報』平成24年9月号掲載より
齢の割には若いなどとおだてられてはいても、あと2年も経たないうちに還暦という現実を突き付けられて少しものの見方、考え方が変わってきた。とりわけ大学生にもなる我が子の生き様と自分の人生も重ね合わせてみると、自分の過去がいくらか俯瞰的に見てきて、かつての自分の中の「定説」に修正が必要になってくる。とりあえず修正しつつある「定説」は二つある。一つは、卒後何故病理を選んだのかということ。もう一つは、もの事が自分を選んでくれていたのではないかということである。
まず第一の問題であるが、私は昭和55年に秋田大学医学部卒業と同時に直ちに病理の大学院へと進んだ。従来、私はその理由として、「"病理の理法"を探求するために」「研究をしたいがために」その道を選んだと考えていた。しかし今になってみると「学生時代の勉強がいまいち納得できなかったから」ではないかと考えるようになった。
子どもたちが、高校や大学での勉強に四苦八苦している姿を目の当りしていると、高校や大学医学部の勉強はしみじみ大変だと思う。事実私にしても、大学受験で一浪したことに至極満足している。それは、よく分からないまま終わってしまった高校時代の勉強を受験という明確な目標を持って、それなりに理解しきって終わらせることが出来た満足感からである。今と違って研修医期間が義務づけられていない時代にあって、卒後直ちにしたかったことは、大学時代に追われいた勉強の根底をなすものは何かを知って得る満足感への渇望だったのだと思う。
私は5年間病理に携わったことを非常に納得している。決して順調な月日ではなかった。学位のテーマが決まらず3ヶ月間筑波大学の病理に国内留学をしたり、なんとか卒論を取り繕って学位は取得したものの研究を本当の意味で仕上げたくて1年間まったくの無給(バイトもない)で研究したりの日々だった。そこでやり終えた達成感は自信にもなったが、病理を続けようという気はすでになくなっていた。御蔭で、その後に北里大学皮膚科入局した折も、また水沢に来てから漢方を通じて内科を学ぶ上でも、あの時の経験が殊の外役立った、さらには子どもたちに勉強する上でのアドバイスができるという特典まで付いてきた。
次の定説は、これまでの人生の選択に当って、他の人の助言はいろいろ聞いてはいるものの最終的には自分で決断したと思ってきた。しかし、我が子の進路の選択やその後の結果を思うとき、もの事がその人を選んでくれている想いに駆られる。
都立の高校を卒業し、自分の学力や科目などから秋田大学を選んで大学院までの約10円間を秋田で過ごし、筑波から自宅に近い北里大の皮膚科学教室へ。北里大での6年の間に水沢出身の家内と結婚。その縁で義祖父・桜井文彦先生の他界により水沢の住人として再び東北の地に戻ってくることとなり、今や約20年にもなる。さらに義父・桜井昭彦先生と同窓生との間がらの師・山田光胤先生の最後の弟子とさせて頂いた。この出合いによって、病理のミクロの世界と、皮膚科で学んだ肉眼で体感される現実の世界、さらには漢方的なマクロの世界と私の求めてきた理想の診療が出来うる手だてを習得することが叶ったような気がする。
水沢に来て水沢にあって長い歴史を誇る桜井内科病院(現在はダウン・サイズして桜井医院)の副院長から院長へと。また皮膚科にあっては岩手県皮膚科医会々長(現在は3期6年間で引退)に。漢方の世界では日本東洋医学会岩手県部会会長にと、最後の決断はあったにせよ成り行き上引き受けさせて頂いた経緯がある。特に漢方にあっては、私の診療所のすぐ横に「留守家医師・坂野氏邸跡」なる小さな石碑が立てられているが、この方も私が学んだ古方派という流儀の祖・吉益東洞の門下の一人であった。さらに奇しくも我が子二人がそれぞれ吉益東洞の子孫と同級生になっているのである。
義祖父の桜井文彦先生は長らく水沢の医師会長もされ、水沢医師会が桜井内科病院に間借りしていた時代もあったとか。故、桜井昭彦先生も水沢医師会の理事として尽力された方であることは会員の多くの方々がご存知のことと思う。私にあってはもともと水沢とは縁もゆかりもないところから、奥州市医師会の方々に支えられて生計を立てる身の上になっている。そのこと一つとっても様々な出会いや出来事の重なりが、ある一つの方向に引き寄せられているとの想いが浮んでくる。まさに運命である。
妻との結婚がなかったら今頃まだ大学にへばり付いていたか、東京近郊の病院の勤務医として定年まではと働いていたことだろう。左様に開業医とは無縁な人間と思い込んでいた。さらには専門分野のこととは言え、その地域の長に推薦されるようなキャラでないことは自分がよく知っている。それでも尚こうしてなんとかやれているのは、患者さんからの信頼や家族の支えも含めて周囲の方々あってのことと感じている。
私のモットーは趣味と実益を兼ねること。日々の診療のどこかに興味や驚きがあるから楽しみもある。それに加えて患者さんからのいくばくかの満足が得られると最高の気分にもなれる。皮膚科や漢方の世界は世代や性別を越えて様々な層の患者さんが来院してくださるので、いろいろな観点で捉えていくと興味の持ち方も多彩である。それにつけても患者さんにも掴む切っ掛けを作って頂きたいと望むのは欲張りすぎだろうか。
足白癬(水虫)について
『胆江日日新聞』2004年7月23日掲載より
水虫はムシによる病気ではありません。 白癬菌というカビの病気です。 したがって、カビの生えやすい梅雨時やムシムシした夏に多いのです。 さらに革靴を一日中履いたり、長靴や安全靴を使う機会の多い人は当然水虫にかかりやすくなります。 また女性のストッキングも通気性が悪く、カビの温床となります。
水虫になると、足の裏に小さな水ぶくれが出来て痒くなったり、足のユビの間がジクジクしたりしてきます。 さらに古くなってくると、足のカワが厚くなってガサガサになりヒビワレの原因になったり、爪が濁って厚くなったりしてきます。 このような年季入りの水虫は、概して痒くなくなってきます。 そうなると「痒くないから水虫でない」と思っている人も案外多くいるものです。
逆に、足が痒いと水虫だと考えて来院される方もいます。 手荒れならぬ“足荒れ”。 つまり足のタダレやカブレだったりする方もいます。 水虫だと思って水虫の薬をぬってカブレたり、水虫からバイ菌(細菌)が入って化膿させてしまい、足全体をまっ赤に脹らしてしまう人もいます。 また、水虫によく似た症状をとる掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)という少し難しい病気もあります。 足のトラブル即水虫ではありません。
診断を決めるのに専門医は、水ぶくれの一部や剥がれかかったヒフをピンセットで取り、顕微鏡で白癬菌(カビ)の存在を確認します。 このような検査をしなければならないのは、見かけだけでは区別のつかない病気もあるからです。
治療は初期のものであれば、抗真菌剤(カビを殺す薬剤)をぬるだけで充分です。 しかしチョットしたコツがあります。 まず広めにぬること。 次に根気よく毎日、見かけが治っても安心しないで最低3ヶ月はぬり続けることです。 治り難いもの、特に爪にまでカビが入って厚くなってしまったものには、飲み薬が効果的です。 現在、主要な飲み薬を大別すると、毎日服用するタイプのものと、月に1週間だけ集中的に服用して、それを何ヶ月かくり返すタイプのものの2つがあります。 患者さんの飲みやすさや、他に薬剤を服用しているか否かなどによって、どのタイプの薬にするかが決められます。 テレビのCMのおかげで、だいぶ水虫の飲み薬も有名になって、家族に促されて受診される爪水虫の患者さんも増えています。
最後に、最近のトピックを1つ。 柔道家やレスリング選手の間で集団発生している、”格闘家白癬”と呼ばれている白癬症があります。 外国との交流試合を通じて感染を起こしたり、また、最近では外国から感染した人が、日本で試合や合同練習といった機会を通じて感染者を拡大させていっているとか。 これらの多くは、足より体の“タムシ”として発症します。
同じようなカビの病気であっても、足では“水虫”、カラダでは“インキン・タムシ”と俗に呼ばれていますが、カビの種類(同じ白癬菌の仲間ではあっても)によって足に出来やすいものや体に多いもの、また頭や顔に特徴を示すものなど細かく見ていくといろいろな病気の型をとってきます。 もちろん足の水虫が体に感染してインキン・タムシになることもあるので、水虫は何んと言っても早目に治しておきましょう。 放って置いて家族から白い目で見られないうちに・・・・。
帯状疱疹について
『胆江日日新聞』2000年8月5日掲載より
水ぼうそうと同じウイルスでおこる帯状疱疹は、前者が主として小児の全身に小さな水ぶくれがたくさん出来るのに対して、大人の身体の片側(身体の縦半分に 割って、そのどちらか)に帯状に並んで集中して、水ぶくれが出来るのが特徴です。 しばしば神経痛のような強い痛みを伴います。
発疹(ほっしん)が出てから三週間ほどで治りはしますが、高齢であったり、痛みが強かったり、発疹の部位が顔や頭、腕や脚だったり、発疹の広がりが広かったりすると痛みや障害が残りやすくなります。
激しい痛みが残りやすそうな人には、特に抗ウイルス剤という特別な薬を、出来るだけ早めに注射したり、服用したり、あるいは入院の必要な場合もあります。 また、疲れやストレス、内臓の病気のために抵抗力が落ちて発症するため、安静にした上で内臓の検査を受けておくことも大切です。
初期の手当てが、その後の病気の治り方を大きく左右しますので、怪しいと思ったら信頼する医師に早速相談してください。
なお、水ぼうそうにかかっていない人が身近にいますと、水ぼうそうの形でうつすこともあります。
ハンセン病について
『胆江日日新聞』2001年6月9日掲載より
数週間前に話題になったハンセン病訴訟。 テレビに映し出された元患者さんの姿は皮膚科医としてある種の衝撃でした。 それは、一つには皮膚病のもつ意味の大きさであり、もう一つは患者さんにとっての病気は過去も現在もなく現実のみがついて回るということでした。
皮膚の病気は、内臓の病気と異なり、常に目にするところに病気があり、治療の良しあしもすぐわかることに特徴があります。 さらに、男性も美容整形を希望 する昨今、心の美しさよりもまず見た目の良しあしが何よりも優先され、これらは精神的な面にも大きく影響してきます。 ハンセン病は、もともと感染しにく く、また治療により治っていく病気でありながら、古くから偏見や差別があったのも、そこにも一因があり、皮膚科医の責任の重大さをあらためて感じさせられ ました。
そして、テレビに映し出された元患者さんの姿の病気の状態は、瘢痕(はんこん)と言って、いわば傷あとです。 私は大学院時代、肉芽腫反応といって、身体 にバイ菌を含めた異物が入ったときの反応を研究していました。 ハンセン病の原因も特殊なバイ菌の一種で、身体の抵抗力の状況によって種々の特徴的な肉芽 腫反応を、とりわけ顔や手・足などの皮膚と神経に示すことで有名で、瘢痕とはその反応の最終的な成れの果ての状態です。 しかし、何分わが国でハンセン病 に新しく発病される患者さんはほとんどなく、また検査法や治療法もおおむね確立していることもあって、私の研究ではハンセン病は知識だけのものでありまし た。 ハンセン病は、私たちの世代の医者にとって、実は過去の病気くらいにしか受け止めていず、事実わが国でハンセン病を専門とする医師の減少を、専門家 の間で大変憂慮されているくらいです。
このような研究面や医療面での問題の如何にかかわらず、かつて必要以上に恐れられ、根こそぎ隔離され、阻害された人たちは、現に生きており、身体の傷跡と 同じように、精神的にも人生そのものも傷を負っていたのです。 ハンセン病にかかわらず、病気になるということは、大小深浅はあるものの、その人の人生に 傷を残し、たとえ病気が治った後でもその人にとっては常に現実の傷となって残るものだと思いました。
ところで、ハンセン病の元患者さんの多くは、抵抗力の低い子供のころに感染の機会があり、長く発病しない期間の後に、大人になってから徐々に病気が出て、らい予防法に基づき国立療養所に入所することになり、老人になるまで何十年と入所しつづけることになったのです。
このらいの予防法は、明治40年に制定され、昭和6年、昭和28年と若干の改正があったもののこの法の下に延々と強制隔離が強行され続けました。 患者さ んの救済というよりも、社会からの完全な排除を目的とされ、ハンセン病予防は患者撲滅からという考え方が根強くあったからのようです。 治療は療養所でな ければ受けられず、一度入所すると退所することはまずなく、子供も産まれないようにされていたとのこと。 時にはひどい制裁が加えられたこともあったと か。 文献を調べていけばいくほど日本社会の閉鎖性に胸がつまる思いです。
昭和62年に国立ハンセン病療養所の所長が嘆願書を出しても、政府に改正の動きは全くなく、平成8年4月1日にようやく「らい予防法」が廃止されました。 この時、法律に「らい」の語は「ハンセン病」へ改正されました。しかし、法律や言葉は変わっても元患者の傷は現実であり続けたのです。 なお、らい予防 法の廃止に当たっては岩手医大昆宰市名誉教授も皮膚科医として尽力されています。
余談となりますが、私が小学生のころ、近所に顔全体を小さいころにヤケドして瘢痕となったご婦人がおりました。 その方はやはり悲嘆にくれていたそうです が、人徳のある先生から「医学が進歩して、きっともっと良くなるから頑張って生きるんだとよ」と励まされて、結婚もして今も健在であるとか。
医者も患者も常に病気を通して人生の勉強をし合い成長し「災い転じて福となす」としたいものです。
薬疹あれこれ
『水沢医師会報』1996年7月号掲載より
数年前にはソリブジン、今や薬害AIDSが騒がれて、薬を飲んで何か異常が起こると直ぐに薬が、さらにはそれを投与した医師が悪者にされかねない昨今である。 読者も、多かれ少なかれ、この“被害者”になったことと思う。
とりわけ皮膚科医は「薬疹」を自らのテリトリーとしている関係上、薬害とは縁が深い。 もっとも初めから「薬疹」と診断できる場合はむしろ少ない。 例え ば全身にびまん性の発疹が出ている場合、各々の感染症特有の発疹の性状(個疹、分布、経過など)をみない非典型的な時などは、薬疹を念頭に置きつつ「中毒 疹」として、まず疑わしい薬剤を中止して、抗ヒスタミン剤の内服やステロイド軟膏の外用でひたすら祈るような気持ちで発疹の退くのを待っている。 あわよ く貼付試験や皮内反応(重篤な場合はこれも危険を伴う)、場合によってはDLST、さらには内服テスト(実際には施行不可能の方が多い)で陽性反応がでれ ば、勝利品の如くに「薬疹」の冠を頂けるのである。 科学者でありたいとの願望からすれば、このような栄冠の下で“アレルギー証明証”を記したいものだと 思っている(実際にはこれらの努力が報われないことも多い)
因みに薬疹が極めて疑わしくても上記試験で反応が出ない場合、「感染症プラス薬疹」即ち、感染症などの免疫賦活状態下で薬剤が反応して発疹の出現をみたと一応は解釈せれている。
もちろん発疹の性状から薬疹がほぼ確定的で尚且、進行性(特にTEN型と呼ばれる重症型)であれば、入院管理下で、迷わずステロイドの全身投与を行っている。 これは当に短期決戦のサバイバル勝負である。
薬疹は軽症から重症まで、また発疹の形態や原因薬剤にしても多種多様である。 「極論すれば、すべての薬剤に薬疹(薬害)を起こしうる可能性がある」とし ばしば患者さんに言ってはいるが、薬疹の患者さんを前にして、それを証明することは結構難しい。 そして、訴訟社会を前に、インフォームド・コンセンサス と理念で理解してはいるものの、実際の患者さんの個性やインテリジェンスに合わせて納得させることは本当に難しい。 いっそ医学部の講座にも「話し方講 座」を作ってみてはどうだろうか。